#003 脳の癖を考慮したクリエイティブ戦略!
- Studio Meguro
- 6月26日
- 読了時間: 6分
更新日:10月21日
私たちは日々、無数の意思決定を行っています。
朝食に何を選ぼうか、仕事でどのようなアプローチを取ろうか、友人の誘いをどうするか...。
これらの決定が、どのように行われているのか、深く考えたことはありますか?
私は普段、深く考えずに無意識で動いていることがほとんどですね。
いちいちそんなこと考えて立ち止まってたらキリがない。。。
そんな日常での私たちの意思決定を行動経済学者のダニエル・カーネマンは、私たちの思考を大きく「システム1」と「システム2」の2つのモードに分類しました。
これらの思考モードを理解することは、顧客の行動を予測し、より効果的なマーケティング戦略を立てる上で非常に重要です。
1. 「システム1」:直感的で衝動的な思考の正体
システム1は、直感的、迅速、無意識的な思考を司るモードです。
これは、過去の経験や知識に基づいて自動的に反応し、ほとんど努力を必要としません。
例えば、突然大きな音に驚いて身をすくめる、目の前の計算式「2+2」の答えを瞬時に導き出す、長年運転している人が無意識にギアチェンジするといった状況でシステム1が働いています。
これにより、私たちは瞬時に判断を下し、日々の活動を効率的に過ごすことができます。
しかし、その迅速さゆえに、ヒューリスティック(経験則)に頼りがちになり、時に「認知バイアス」と呼ばれる偏った判断を引き起こすこともあります。
消費者行動への影響(システム1が働く場面)
スーパーマーケットでの買い物は、システム1が活発に働く典型的な例です。
商品の「見た目」:陳列棚で色鮮やかなパッケージや、目を引くキャッチコピーを見ると、「美味しそう!」「お得そう!」と感じ、深く考えずにカゴに入れることがあります。
慣れ親しんだブランド:いつも買っているお気に入りのブランドや、CMでよく見かける商品を見ると、安心感から反射的に手に取ってしまうことがあります。
緊急性や限定性:「本日限り半額!」「残りわずか!」といった表示を見ると、考える間もなく「買わなきゃ損!」という気持ちになり、衝動的に購入してしまうことがあります。
価格のアンカリング:「通常価格2,000円が今だけ1,000円!」という表示を見ると、元の価格に意識が引っ張られ(アンカリング効果)、それが本当に自分に必要なものか、あるいは本当に安いのか深く考えずに「安い!」と感じてしまうことがあります。
これらはすべて、顧客のシステム1に働きかけるマーケティング戦略の例です。
システム1は、感情的で、迅速で、無意識的な判断を下すため、視覚的な魅力、ブランドの信頼性、緊急性、そして価格の提示方法が非常に重要になります。
2. 「システム2」:分析的で熟慮的な思考の深掘り
一方、システム2は、分析的、熟慮的、意識的な思考を司るモードです。
システム1では処理しきれない、より複雑な問題に直面した際に発動します。システム2は、意識的な努力と集中力を必要とし、システム1よりもはるかに遅く、エネルギーも消費しますが、その分、より論理的で正確な判断を下すことが可能です。
例えば、複雑な数学の問題を解く、新しい言語を学ぶ際に文法を理解しようとする、複数の選択肢の中から、それぞれのメリット・デメリットを比較して最良の決定を下すといった状況でシステム2が働いています。
消費者行動への影響(システム2が働く場面)
高額な買い物や複雑なサービス契約は、システム2が中心となる消費者行動の例です。
高額商品の購入:新しい家電製品や高機能な調理器具など、高額な商品や長く使うものを選ぶ際、性能、省エネ性、保証期間、レビュー評価などを比較検討し、様々な情報を集めて熟慮します。
初めての購入:今まで使ったことのない新しいジャンルの商品やサービスを試す際、インターネットで詳細な商品説明を読んだり、口コミサイトで評判を調べたり、競合他社の商品と比較検討したりします。
複雑なサービス契約:スマートフォンのプラン変更や保険の加入など、多くの選択肢と専門用語が含まれる契約の場合、提供されるサービス内容、料金体系、解約条件などを注意深く読み込み、不明な点は店員に質問して納得するまで考えます。
これらはすべて、顧客のシステム2に働きかけるマーケティング戦略の例です。
システム2は、論理的で、分析的な判断を下すため、詳細な情報提供、客観的なデータ、論理的なメリットの説明、そして顧客の疑問に答える丁寧なコミュニケーションが求められます。
3. 経営者は「システム1」と「システム2」をどうマーケティングに活用すべきか?
ダニエル・カーネマンは、システム1とシステム2が独立して機能するのではなく、常に相互作用していると述べています。
通常、システム1がまず問題に対応し迅速な解決策を提示し、システム1で解決できない場合や、システム1の出した答えに疑問が生じた場合にシステム2が介入して詳細な分析を行う、という流れです。
この相互作用を理解し、顧客の思考プロセス全体に働きかけることが、効果的なマーケティングには不可欠です。
(1) システム1に訴えかける(衝動買いやブランド定着を促す)
強力な視覚的要素:魅力的なパッケージデザイン、目を引く広告ビジュアル、動画コンテンツを活用しましょう。
感情に訴えるメッセージ:ストーリーテリング、共感を呼ぶコピー、ユーモアを取り入れ、顧客の感情に直接語りかけましょう。
シンプルで分かりやすいオファー:限定セール、特典、初回限定価格など、分かりやすく魅力的な提案を打ち出しましょう。
ブランドの確立:認知度を高め、信頼感を醸成し、顧客の「お気に入り」となることを目指しましょう。
社会的証明:「売上No.1」「〇〇賞受賞」など、他者の行動や評価を示すことで安心感を与えましょう。
(2) システム2をサポートする(信頼構築と納得感を与える)
詳細な情報提供:製品のスペック、成分表示、利用ガイド、FAQなど、顧客の疑問を解消できる網羅的な情報を提供しましょう。
客観的なデータと証拠:性能テストの結果、研究データ、顧客の声(具体的な成功事例)など、客観的なデータと証拠を示し、信頼性を高めましょう。
論理的なメリットの説明:「なぜこの商品があなたに必要なのか」「他の商品との違いは何か」を明確に提示し、論理的な納得感を与えましょう。
比較機能やデモ:他社製品との比較表、実際に試せるデモンストレーション機会を提供し、慎重な検討をサポートしましょう。
専門家による解説:製品の専門家や開発者による解説動画や記事を用意し、深い知識や背景を伝えましょう。
まとめ
顧客がどのような段階で、どのようなタイプの製品やサービスに興味を持っているかによって、どちらのシステムに重点を置くべきかは異なります。
しかし、最終的には、システム1で注意を引き、システム2で納得感を与えることで、顧客は安心して購入し、長期的な関係を築くことができるでしょう。
経営者は、これらの戦略を組み合わせて、顧客の思考プロセス全体に働きかけることが重要です。
あなたのビジネスや製品では、システム1とシステム2のどちらに重点を置いたマーケティングを行っていますか?ぜひ、この思考モデルを日々の戦略に取り入れてみてください。



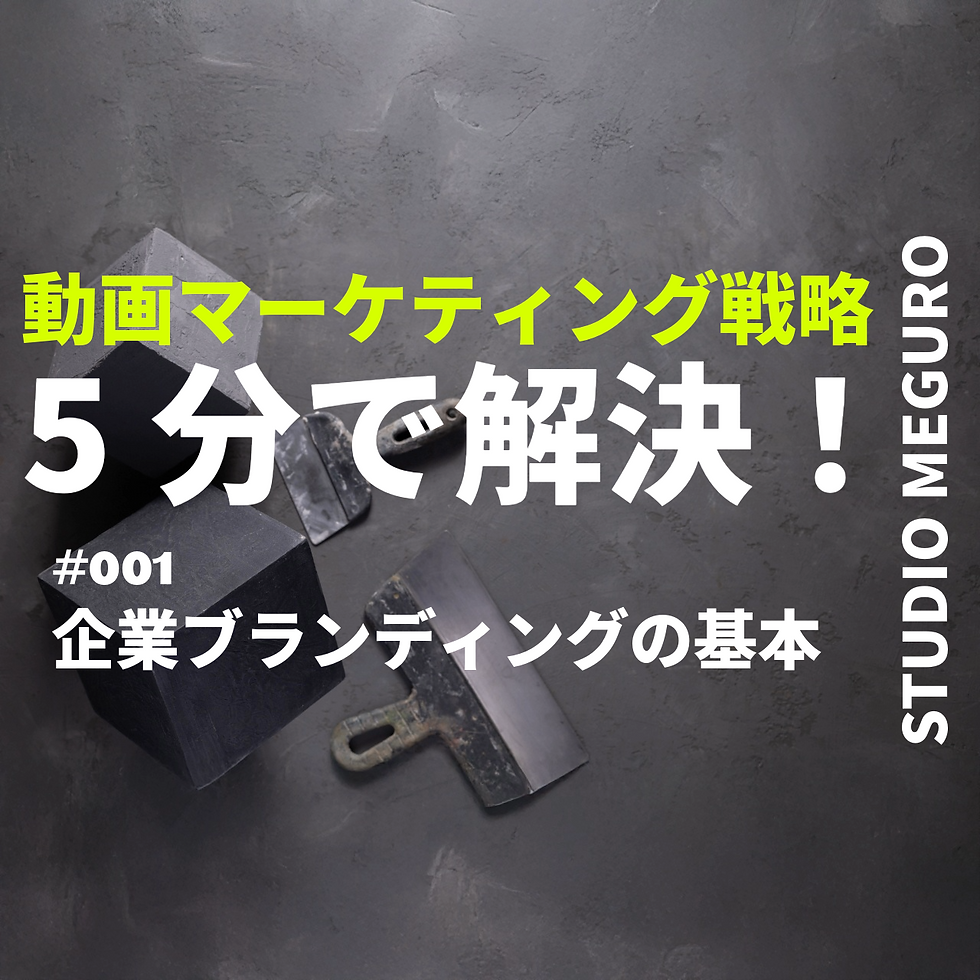
コメント